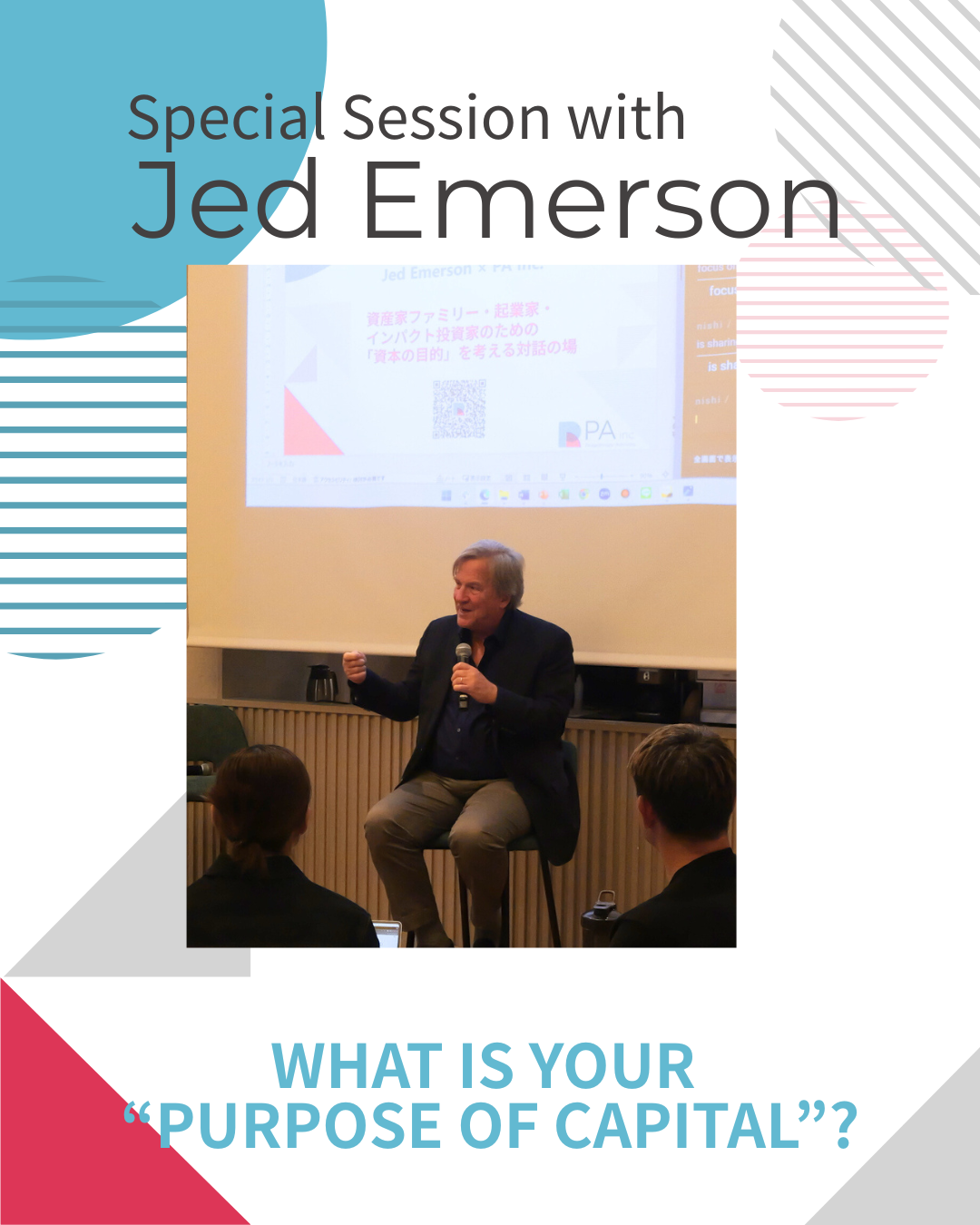KNOWLEDGE
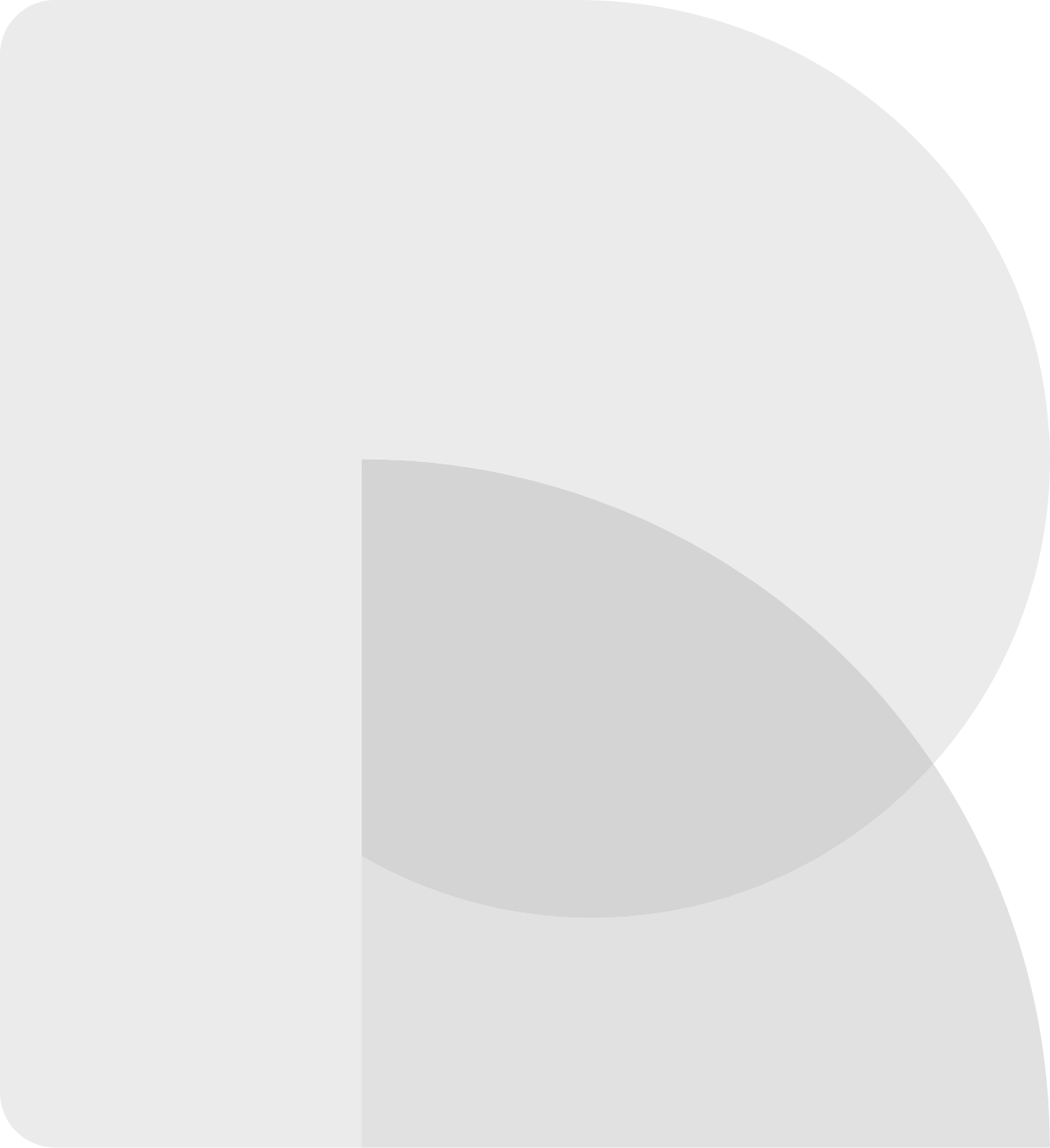
髙山芳之さん ファミリーオフィスを通じた、次世代へ残る価値創造への挑戦。

プロフィール
髙山 芳之(たかやま よしゆき)
株式会社マーブル取締役会長
慶應義塾大学経済学部卒業後、サンフランシスコ州立大学コンピュータ・インフォメーションサイエンス学部を修了。2003年に東京コンピュータサービス株式会社取締役、2005年にTCSホールディングス株式会社取締役に就任し、2018年には同ホールディングス、東京コンピュータサービス株式会社(現・株式会社マーブル)、Total Computing Solutions of America, Inc.の各社で代表取締役を務めるとともにムトーアイテックス株式会社取締役を兼任。2024年10月より株式会社マーブル取締役会長(現職)。
TCSホールディングス㈱は髙山芳之さんの父である髙山允伯さんが一代で事業を大きくし、プライベート会社として亡くなる直前まで経営を続けていました。先代から多くを継承した芳之さんはファミリーオフィスを設立し、一族としての今後を模索しています。
ファミリーオフィスとは、有形資産の管理運用から価値観や使命などの無形資産まで、一族が今後も発展するための仕組みをつくる組織のことです。
ファミリーオフィスの一環として「TCS奨学会」等のフィランソロピーを実行している髙山芳之さんに、お話を伺いました。
ファミリーオフィス設立に至った経緯を教えてください。
― 継承した資産を、次に繋げるために始めたのがファミリーオフィス
父である髙山允伯(たかやままさのり)が、TCSホールディングス株式会社(現・代表取締役社長髙山芳之)の創業者として事業規模をかなり大きくし、しかも100%プライベート会社のまま経営していました。父は亡くなるその日まで社長をやっていたので、8年程前に父を亡くしたと同時に、文字通り全てを(主に我々兄弟で)継承することになりました。ですので当時は、まず目の前の事業をなんとかしなければいけないということで、非常にバタバタとした日々を過ごしていました。
トップとして経営をしていく中で、グループ全体を見回した時に“1つの資本のもとにある”という状態が必ずしも得策ではない、と私の意識が徐々に変化していきました。そこで、「全てに変革のメスを入れよう」と決意しPEファンドとの提携によってそれを実行しました。その結果、それまで個人の株だったものに一気に流動性が出ました。流動性が出たこと自体はめでたいのですが、我々兄弟はすぐに引退する年齢ではないので、今後の一族や社会のために何か行動をしなければという意識が芽生え始めました。
父の代でプライベート会社としてこれだけ広げた事業や資産を、フィランソロピーも含め形を変えて次に繋げるために始めたのがファミリーオフィスです。ですので、最初からファミリーオフィスにしようとして始めたのではなく、今後の流れを考えた時に自然とこういう形になりました。
フィランソロピーを、大事なものとしてお考えになっているのはなぜでしょうか?
― 世に残る価値を創造し、家族として結束するために、フィランソロピーに取り組んでいます
私の場合は、まず目の前の事業に取り組むという課題があり、その延長線上にファミリーオフィス設立がありました。
私たち兄弟は創業者である父のことを近くで見てきたので、父の価値観もなんとなく把握しています。ですが、我々が引退して一族の新しい世代に引き継いだ時に、髙山家が大事にしている価値観やマインドがよくわからないままだと、大きな決断をするのが難しいと思うんです。創業者は何かしらの“想い”があって事業をスタートさせますが、それを引き継ぐ立場の2代目3代目…は、ある意味社会から生かされているのだから、社会に価値を提示できる存在にならなければいけないと思っています。それに、次世代のファミリーメンバーが家族として一つであり続けられるのか、という不安も正直なところ持っています。というのは、次世代の家族がもしも経済合理性だけを優先して資産管理をすることになれば、決断も鈍るし、髙山家のアイデンティティを保ち続けるのは難しいのではないかと…。なので、家族として何かしらのバインドが必要であるならば、その一つとして(世の中から必要とされる)フィランソロピーが良いのではないかと考え、取り組んでいます。
自分が受け取って残す立場になったからこそ感じるのですが、いくら後世に残したいと思ったとしても、結局「残る」ものじゃないと残らないんです。世の中から必要とされたり、みんなが良いと思ったりするものでないと残らない。社会に残る価値をつくり、ファミリーとして結束するためにも、フィランソロピーを大事にしていきたいです。
とはいえ、現段階で具体的な方針があるわけではないですし、税務上の問題も含めてきちんと考えたいと思っています。要はファミリーオフィスのお金の使い方として、我々ファミリーが腹落ちするのかどうかを一番に考えて、今後の動きを決めていこうと思っています。
「TCS奨学会」の活動目的と今後の課題について教えてください。
― フィランソロピーと事業活動でシナジーを生み出すか否か。目的と方法の見直しが今後の課題
「一般財団法人TCS奨学会」は、会社の経営理念である「情報社会の明日を創造・建設し、世界経済の発展と人類社会の福祉向上に貢献する」有用な人材を育成することを目的として設立しました。活動内容は、学術優秀かつ経済的理由により就学困難な学生(大学2~4年生、大学院1~2年生)を対象に年30名を選出し1人60万円の奨学金を給付しています。
(出典:一般財団法人TCS奨学会)
この事業は、父が生前に学生を支援する活動を検討していたので、その想いを引き継いだという面と、そしてTCSホールディングス㈱へのファンとなっていただけることにも繋げられればと思っていました。
ありがたいことに、多くの優秀な学生たちが応募してくれているので、倍率が非常に高くなっています。奨学会の設立が2020年の10月なのですが、ちょうどコロナと重なって学生たちがアルバイトもできず経済的に困窮していたというのと、時代的な流れもあり、例えば「サークル活動なんてお金がなくてできません」という学生たちが増えていた時期だったんです。TCSホールディングス㈱としてファンになって欲しいと思っているのは、技術者であって、研究者とかR&Dの人材とは、事業という面では少し縁遠いかもしれません。ただ選考を行うと成績で判断するので研究者向きの人が選ばれることがどうしても多くなります。なので、選出される学生の層と、グループのファンとなって欲しい層とでギャップが出ているというのが現状です。あと、倍率が高すぎて「頑張って応募したのに落ちてしまった」という印象が付いている可能性があるので、その辺りのフォローアップをどうするかも今後の課題の一つです。
今後ファミリーオフィスとして取り組みたいテーマはどういったものでしょうか?
― ファミリーオフィス内の枠組みを整え、(髙山家として)最適なフィランソロピーの道を探りたい
私個人としては、まずはファミリーオフィス全体の枠組みを整えねばと思っています。他のメンバーの考えはそれぞれにあると思うのですが、私はファミリーオフィスを含めた全体のことを考える担当なので。
家族で取り組んでいるある分野への支援活動も、弟が代表理事を務めている「奨学会」の活動も、それぞれに課題が色々とあるので、どう塩梅を取っていくのかが難しいところですね。あとは実際に行動しながら、自分たちのファミリーオフィスらしいフィランソロピーの道を探っていくしかないかなと思っています。
そういった意味で、母のフィランソロピー活動について議論するために月に一度ディスカッションをすることが、(家族が)お互いの価値観を擦り合わせたり合意をとったりする良い機会になっていると思います。とはいえ、フィランソロピーについては勉強中ですので、他の方々がどのように活動しているのか、とても気になります。実際にフィランソロピストの方々の活動を伺うことで、今後の参考にしたいです。
TOP