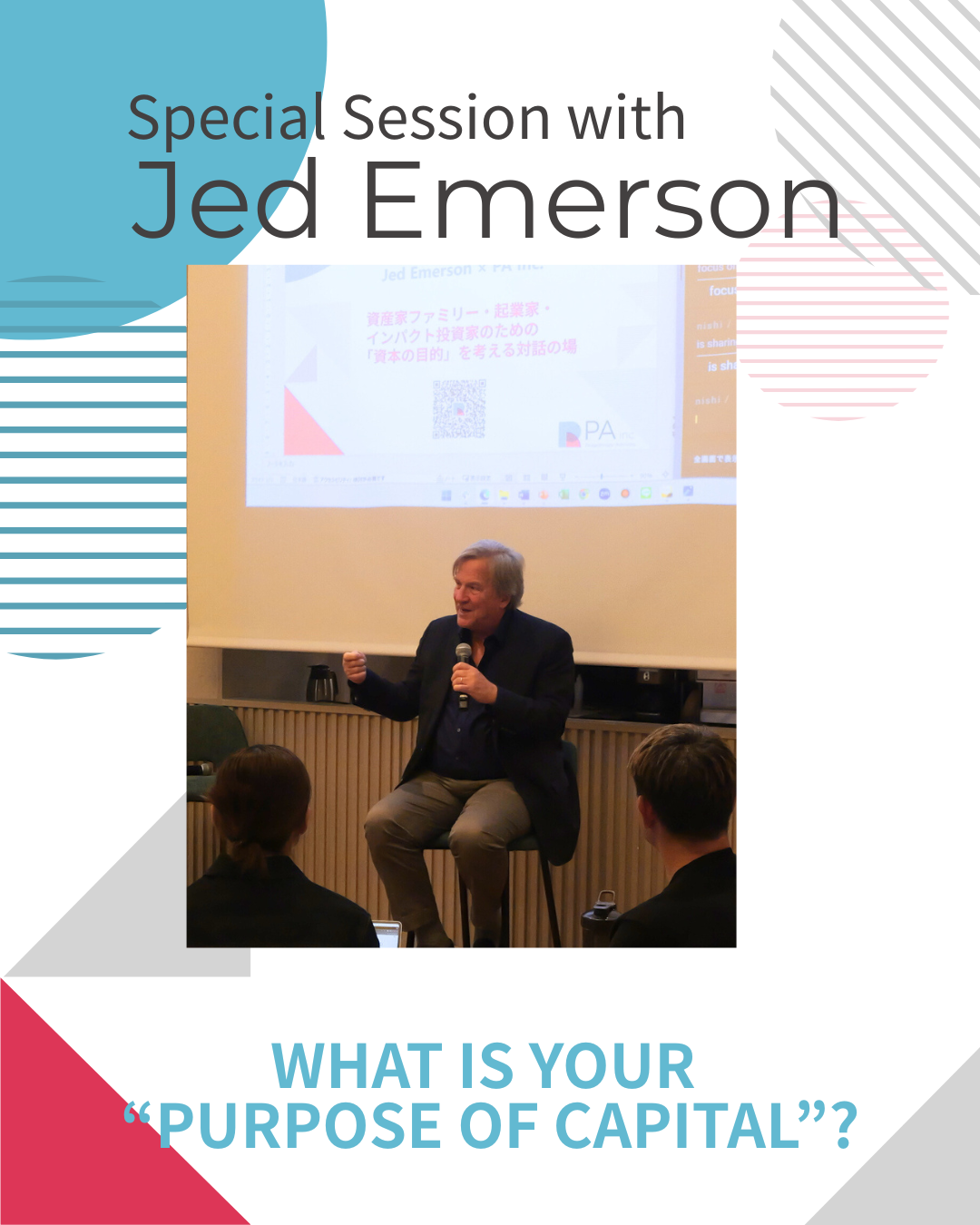KNOWLEDGE
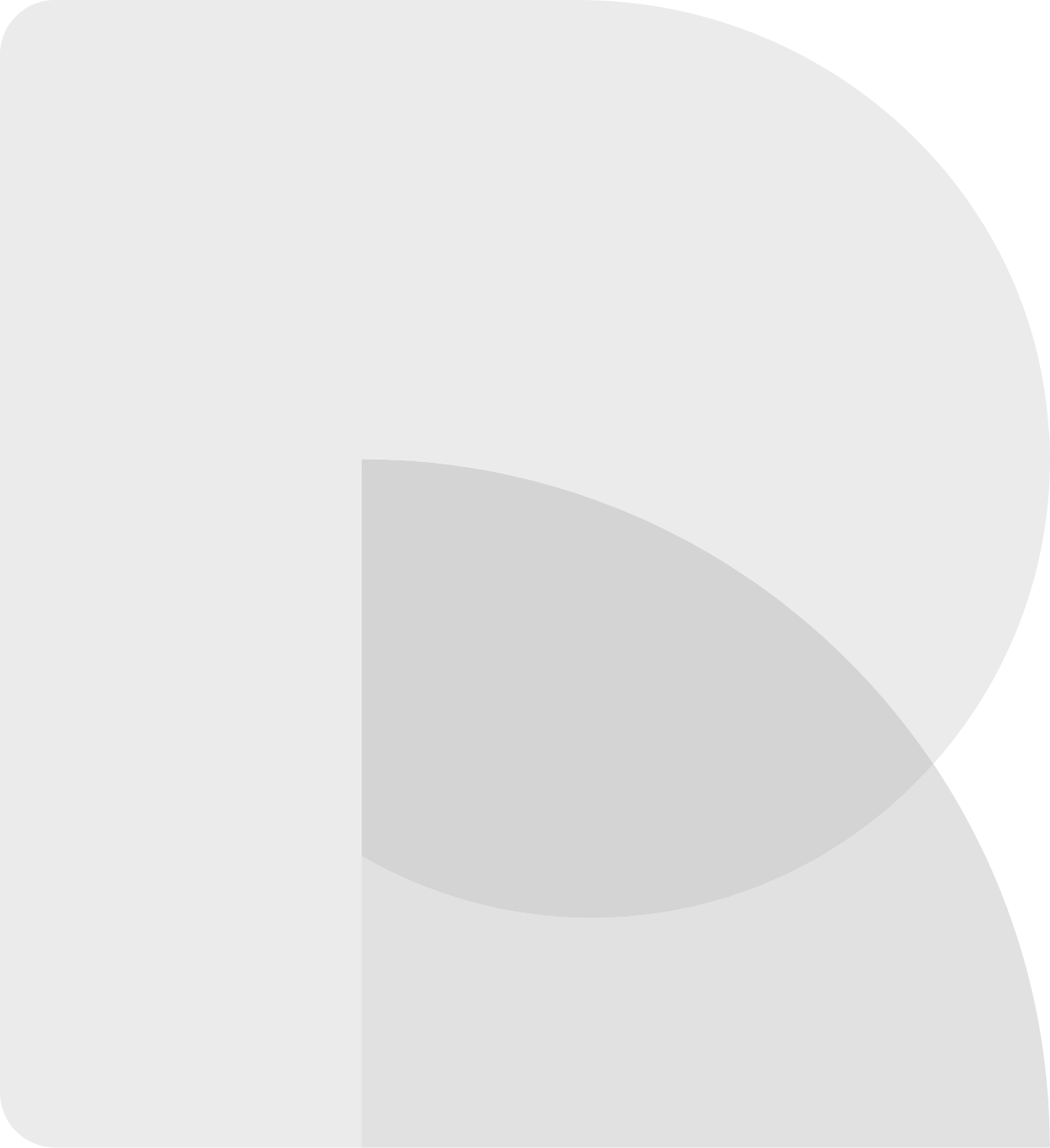
なぜ今、「インパクト評価」が求められているのか
はじめに
社会課題が複雑化・多様化する中で、インパクト評価の導入が注目されています。インパクト評価を通して、「現在地」や「目指す方向」を明確にした上で中長期的な戦略を立てることは、非常に有効な手立てです。
本稿では、インパクト評価の定義と意義を理解した上で、現場での導入背景や効果の分析を通じて、その可能性について検討します。

インパクト評価とは
社会的インパクト評価とは、事業や活動の短期・中期・長期における変化を含めた結果から生じた「社会的・環境的な変化、便益、学び、その他の効果」を、定量的・定性的に把握し、測定する評価手法です。
「評価」という言葉から、「この事業は良いのか、悪いのか」といった成績をつけられるような印象を持たれる方も多いと思いますが、本質的には「自分たちの現在地と向かっている方向をチェックする」ためのものです。(最近では、「評価」という言葉が生むイメージから、インパクト評価ではなく、インパクトを「測定し、その後の事業のマネジメントに活用する」という意味で「インパクト測定・マネジメント(IMM)」という言葉も主流になっています。)
インパクト評価を行うことは、自団体独自の「地図」を描き直す試みであり、その地図をもとに確かな足取りで社会課題に向き合うことは、自団体にとってもステークホルダーや社会全体にとっても、非常に意義深いことです。

初めてインパクト評価を行う際には、第三者の支援を受けることも有効です。その場合、「客観的な視点から戦略の全体像を描ける」「外部ステークホルダーへの聞き取りがしやすくなる」といったメリットがあります。
ただし、インパクト評価やレポートの作成は定期的に行うことが重要です。したがって、毎回外部に依頼するのではなく、手法を理解した上で、内部メンバーが実施することが望ましいと考えます。海外の財団では、数年に一度大切なタイミングのみ外部専門家を起用し、通常は内部スタッフが評価を行う体制が一般的です。共同代表の私がコンサルタントとして勤務していたオープン・ソサエティ財団では、普段は内部でインパクトの測定や管理をしつつ、4年に一度、戦略を大きく見直すタイミングで外部のコンサルタントを起用し、全面的に事業の振り返りと見直しを行うという事をしていました。
日本におけるインパクト評価の導入背景と課題
― ゴールは、自団体の「現在地」と「目指す方向」を正確に把握すること
日本におけるインパクト評価の導入は、およそ10年前から始まりました。特に非営利の領域においては、「資金提供者が支援先のインパクトを把握したい」と考えるのは自然なことであり、提出資料としてインパクト評価を求める資金提供団体も増えてきています。社会全体として、インパクト評価の重要性が認識されてきているのは良い傾向ですが、もし“数字ありき”の評価にとらわれてしまえば、本末転倒だと考えます。
あくまでもゴールは、「自分たちが目指している方向と現在地を正確に把握すること」であり、もしズレているのであれば、その調整にインパクト評価を活用することが重要です。つまり、ビジネスにおけるPDCAを回すための手段として活用するということです。
また、フィランソロピー業界において私が特に課題だと感じているのは、資金提供者自身によるインパクト評価の実施がまだまだ少ないという点です。「どのような課題を解決したいのか」「(支援先を通じて)どのような変化を目指しているのか」といった観点を明確にするためにも、資金提供者自身がインパクト評価を行うことが非常に重要だと考えます。
インパクト評価は、営利・非営利を問わず、また被支援団体・資金提供団体を問わず、今後さらに重要性が高まると予想されます。

現場のリアル:どのようなきっかけで、インパクト評価を始めるのか
― 指針がブレた際に、見つめ直す手段として有効
インパクト評価の導入は、必ずしも初めからその必要性を明確に意識して始まるわけではありません。
例えば、歴史ある財団においては、創業者が亡くなった後、当初の目的や情熱を見失ってしまっている場合もあります。日々のオペレーションに追われる中、「このままでは良くない」と感じていても、何を基準に指針を定めればよいのかがわからず、話し合いのできる相手も失われてしまっていることがあります。その一方で、多くの財団は半永久的に存続することを前提に設立されているため、事業を止めるわけにもいかず、迷いながらも運営を続けているケースが見られます。
また、財団の予算が増えたことで「このお金をどのように使えばよいか」とご相談に来られる場合もあります。
このようなケースにおいても、まず現状を整理し、目指す方向を明確にする手段として、インパクト評価をおすすめしています。
インパクト評価を行うメリットとは?
― 「内部の合意形成プロセス」と「方向性の確認・再定義」
インパクト評価のメリットはさまざまありますが、主に「内部の合意形成プロセス」と「自団体の方向性や取り組みが適切であるかを確認する手段」の二点において大きなメリットがあります。
内部の合意形成プロセス
たとえば財団の場合、チームメンバーが複数いることが多く、実は一人ひとりが思い描いている「最終的に目指すもの」が意外とバラバラであることがあります。インパクトマネジメントを行う際には、ロジックモデル*という評価ツールを用いるのですが、その構築プロセスを通じて、メンバー間の認識の違いを明確にし、歩調を合わせることができます。
組織の方向性の確認と再定義
また、「社会が何を必要としていて、どの方向に進むべきか」、つまり俯瞰した視点での「戦略図」を描くことは、どの団体にとってもなかなか大変な作業です。インパクト評価作成のプロセスを通じて、丁寧に手順を追うことで、目指す方向性を確認し自団体を再定義していくことができます。
*ロジックモデル:ある施策がその目的を達成するまでの因果関係を論理的に整理し、「何のために、何をするのか」「どのような成果が得られるのか」を示すフレームワークのこと。

まとめ
インパクト評価は、数年に一度、定期的に行うことが重要です。ロジックモデルは、その当時の仮説をもとに描かれた地図であるため、時間が経ち状況が変化すれば、その仮説の検証も難しくなります。また、団体が掲げる課題も成長とともに進化すべきであるため、インパクト評価は一度行って終わりではなく、継続的に実施し、年々アップデートしていくことが大切です。
これまで一度もインパクト評価を行ったことがない団体であっても、まずは一度取り組むことで、自分たちが「わかっているつもりだったこと」に新たな光が当たる可能性があります。また、すでに評価を実施した経験がある団体も、たとえ時間が空いていたとしても、継続して行うことでこれまでの軌跡を可視化し、今後進むべき方向をより明確にできるでしょう。
フィランソロピー・アドバイザーズは財団などの非営利組織以外にも上場企業のインパクト評価を実施しております。分野や組織形態を問わず、すべての団体が自身の産み出しているインパクトを理解し、意図した方向に軌道修正を繰り返すことを継続的に実施することが当たり前になることで、社会全体がより良い方向へと進んでいくと考えています。
Co-CEO 小柴優子
※次回はインパクト評価の具体的な事例をご紹介します。
TOP