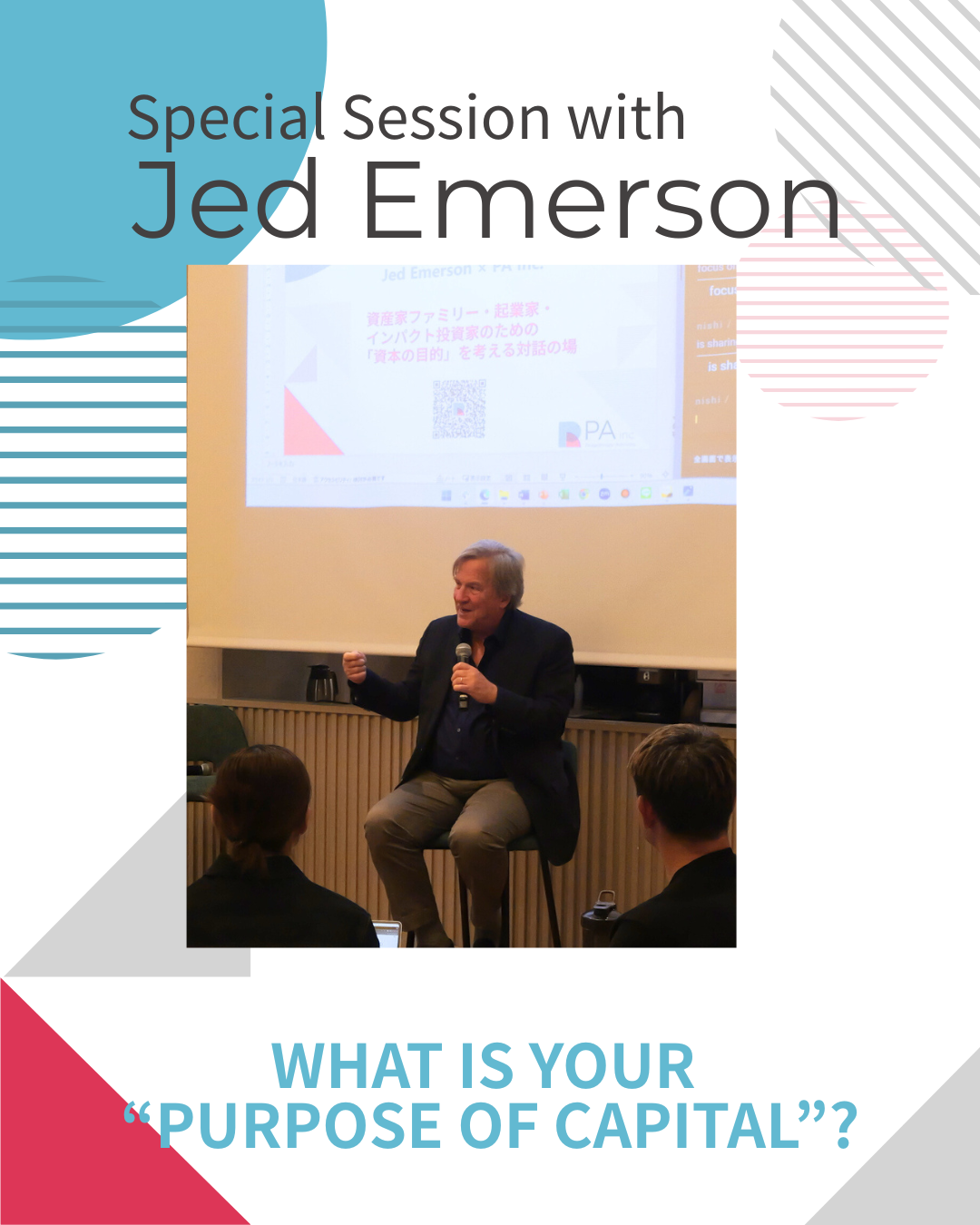KNOWLEDGE
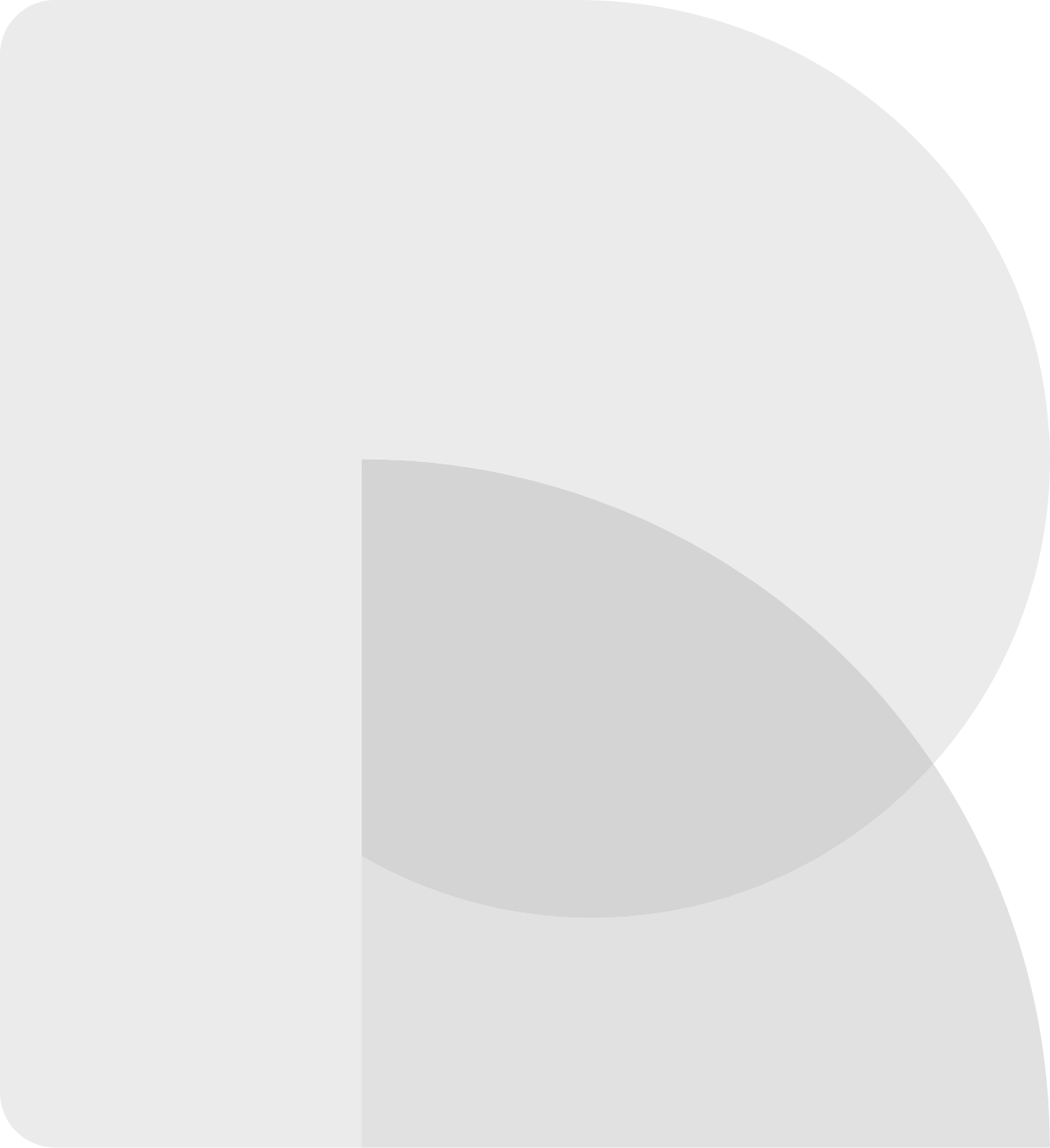
支援に必要なのは「管理」より「信頼」──Trust-Based Philanthropyという選択肢
はじめに
資金提供者は、どこまで支援先を「信じる」ことができるのか。
この問いは、フィランソロピーに関わる誰にとっても、一度はぶつかるテーマかもしれません。成果を出すために、どうすれば資金を「正しく」使ってもらえるかを考え、ルールを定め、報告書を読み込む──。こうした管理型の支援のあり方が、ある意味では当然とされてきました。
けれども今、特に海外を中心に、そうした従来型の支援スタイルに疑問を投げかける動きが広がっています。注目されているのが「Trust-Based Philanthropy(TBP)」という考え方です。
直訳すれば「信頼に基づくフィランソロピー」。聞き慣れない言葉かもしれませんが、そこにあるのは極めてシンプルで、人間的な問いかけです。
TBPとは何か:信頼を出発点とする支援スタイル
TBPは資金提供者の「従来の支援スタイルが不均等なパワーバランスを生んでいるのではないか」と問い始めたことがきっかけで生まれました。より公平に資金を分配し、フェアで包括的なアプローチを模索するために、「現場のことは現場が一番よく知っている」という前提で、受給団体のニーズと専門知識を優先します。そのため、資金提供者は必要以上に指示や制限を加えず、信頼をもって資源を託す、という仕組みです。
TBPを理念にとどめず、実践に落とし込むために、次の6つの原則が提唱されています。
実践原則:信頼を行動に変える6つの原則
- 無制限な資金の提供
- 助成金を運営費・人件費など自由に活用できるようにすることで、受給者にとって最も必要なところにリソースを割けるようにし、影響力がある活動ができる余裕を作ります。
- 複数年の支援
- 単年度ではなく、2〜5年などの中長期支援で団体の安定性を確保します。
- 簡素な手続き
- 申請書・報告書の簡略化により、助成金管理や関連事務に費やす時間や労力を減らし、活動やプログラムそのものに注力できるようにします。
- 関係性の構築
- 透明性のあるコミュニケーションを保ち、訪問・対話・フィードバックを通じて信頼を育てます。
- 意思決定権の委譲
- 現場の判断を尊重し、支援者の介入を最小限に抑えることで、受給者が自分たちで意思決定を行い、変化に柔軟に対応することを可能にします。
- 資金提供者自身も学ぶ
- 支援者もフィードバックを受けることで、自らも変わっていく姿勢を持ちつづけます。
これらの原則により、受給団体の組織力を高め、より長く続く社会的インパクトを目指していきます。
なぜ今、TBPが求められるのか
TBPが注目されるようになった背景には、複数の社会的変化があります。特に新型コロナウイルスによるパンデミックで、資金提供の硬直性に対する課題が浮き彫りになりました。
多くのNPOが、急変するニーズに応えるためには「柔軟に使える資金」と「申請・報告手続きの簡素化」が不可欠であることを実感しました。一方、従来型の助成では、使途が厳格に指定されていたり、成果を過度に求められたりするため、現場の迅速な対応が難しい場面も少なくありませんでした。
また、近年の社会課題は、数値化しにくい複雑な構造を伴うものが増えています。多様性を活かせる包摂的な社会づくり、気候変動への対応、社会の構造変化といった長期的な課題に対しては、現場の柔軟性を最大限に生かす支援が必要とされています。
「信頼」だけでは成立しない:TBPにおける選定基準
もちろん、TBPは「手放しの自由」ではありません。むしろ、最初の段階で丁寧な見極めが求められます。信頼できる支援先を選ぶために、資金提供者は次のような基準を用いることが多いです。たとえば、
- ミッションへの深い共感
- 組織の誠実さと透明性
- 現場・コミュニティとのつながり
- 学び続ける姿勢と柔軟性
スタンフォード・ソーシャル・イノベーション・レビュー(SSIR)に掲載された記事 “The Strategic Value of Trust-Based Philanthropy” によれば、TBPは成果を甘く見るスタイルではなく、「戦略的柔軟性」を最大化するアプローチと位置づけられています。信頼されている団体は、変化に迅速に対応し、新たな機会を捉えることができるという指摘は、多くの実践者の経験と一致します。
国内事例:フィッシュファミリー財団とみてね基金
TBPは欧米を中心に広がっていますが、日本国内でもその理念を実践する財団が登場しています。
フィッシュファミリー財団
米国ボストンに本部を置く同財団は、2003年より日本の女性リーダー育成を目的とした「JWLI(Japanese Women’s Leadership Initiative)」を展開。以下のような支援を実施しています。
- フェローシップ(選出された女性リーダーへの海外研修とメンターシップによる伴奏支援)
- アワード(社会問題や地域課題の解決に貢献する女性の表彰)
- ブートキャンプ(リーダー育成のための研修)
- スカラーシップ(移民・難民の背景を持つ女性に向けた給付型奨学金およびサポート)
これらの幅広い支援活動は、支援対象者とは事務的な関係ではなく、長期的な信頼関係を築くことを目指しており、まさにTBPの価値観が体現されています。
みてね基金
「家族アルバム みてね」の創業者・笠原健治氏の個人資金によって設立されたみてね基金は、2020年に活動を開始し、2025年に一般財団法人化しました。子どもと家族の幸福に貢献する非営利団体を対象に、ステージに応じた柔軟な助成を行っています。
- ステップアップ助成(2年間・最大1千万円)
- 事業基盤や組織基盤を固めるための支援
- イノベーション助成(3年間・最大1億円)
- 取り組みを進めるための投資的支援
継続助成(既存支援先への追加支援)
など、長期支援であることや、事業目的に沿えば使途に制限はないという柔軟性から、信頼を重視した枠組みであることがわかります。申請や報告も簡素化され、受給者とのコミュニケーションを重視する姿勢が一貫しています。
代表理事の笠原健治さんは、ホームページで以下のように書かれています。
「みてね基金」は助成先団体と同じ目線に立ち、信頼することを大事にしてきました。Trust-Based Philanthropy (信頼に基づく慈善運動)に基づいた考え方です。
「みてね基金」と助成先団体は、社会課題を解決するために資金を提供する側と資金を活用する側という立場の違いはありますが、「すべての子ども、その家族が幸せに暮らせる世界を目指して」、共に試行錯誤している仲間であると考えています。だからこそ、助成先団体の状況にあわせた伴走支援、複数年の助成期間、比較的大きい資金の提供、自由度が高い資金使途、申請時計画よりも将来の成果重視、など助成先団体にとって使いやすい、活動しやすい支援の在り方を意識し、実践してきました。
TBPをご自身の団体に落とし込み、2020年4月からの活動で継続して実践されているみてね基金の活動は日本における素晴らしい事例です。
上記2つの例を見ても、信頼は理念ではなく「行動を通じて示すもの」なのだと言えます。
TBPが直面する課題
TBPは理想的に聞こえる一方で、現実的な課題も存在します。
- 「信頼して任せる」ことに不安を感じる資金提供者は少なくありません。
- 無制限資金に対して、成果や説明責任をどう担保するかはまだ議論の余地がありますが必要な部分です。
- 支援者が従来の支援の管理型から意識を切り替え、支援者も学ぶ姿勢を持つための、組織文化の変化も必要です。
重要なのは「正解を探しながら、対話を続ける姿勢」にあります。TBPは、結果よりもプロセスを重視しているとも言えるでしょう。
おわりに
Trust-Based Philanthropyは、「資金提供者は善意の管理者である」という旧来の発想から一歩踏み出し、「支援とは信頼関係の構築である」と捉え直す試みです。
完璧な支援モデルではないかもしれませんが、「信じる」という行為にこそ、大きな変化の可能性が宿っている──。そんな価値観に共感する資金提供者が増えたとき、フィランソロピーはさらに豊かで、人間的なものへと変わっていくのではないでしょうか。
TOP