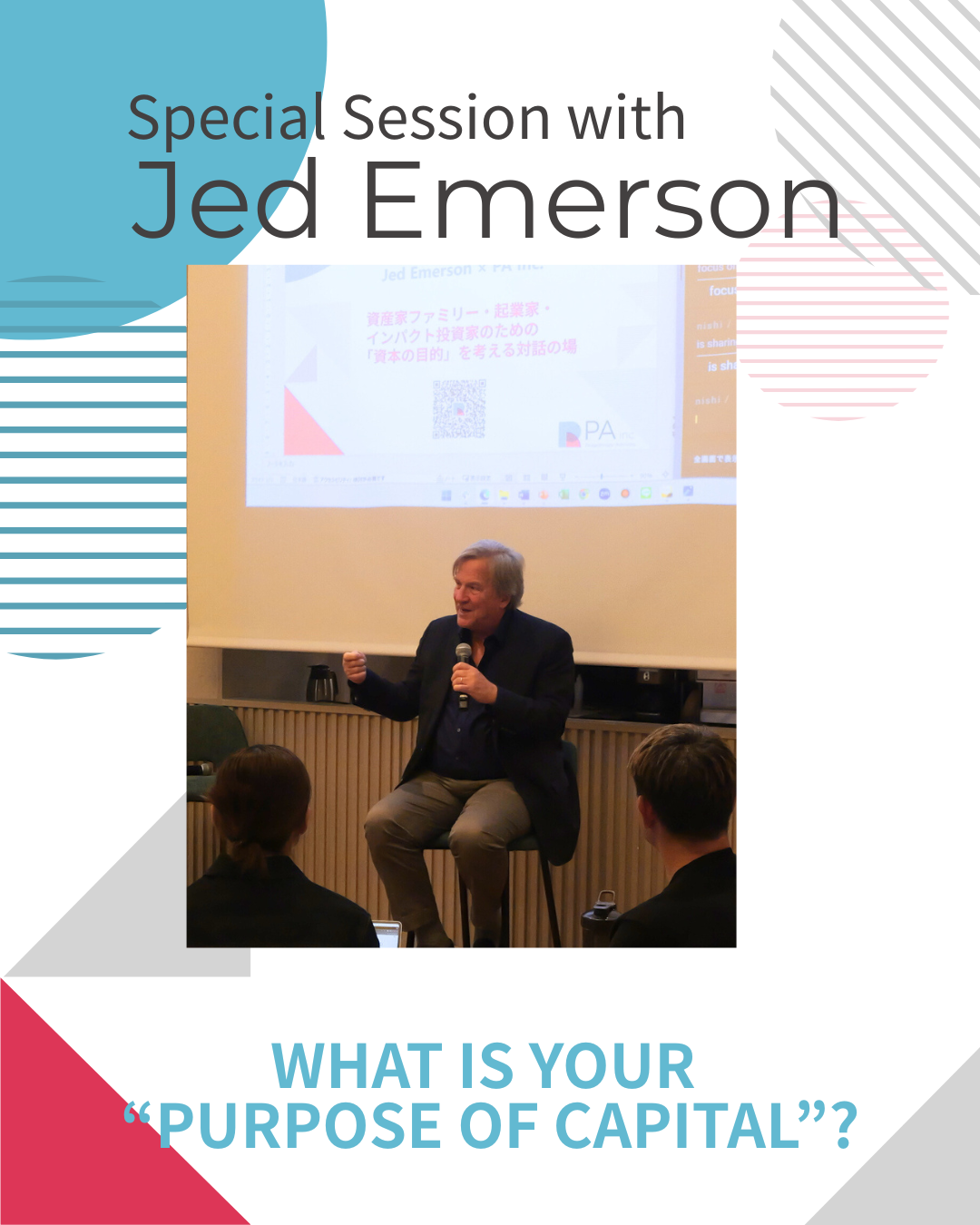KNOWLEDGE
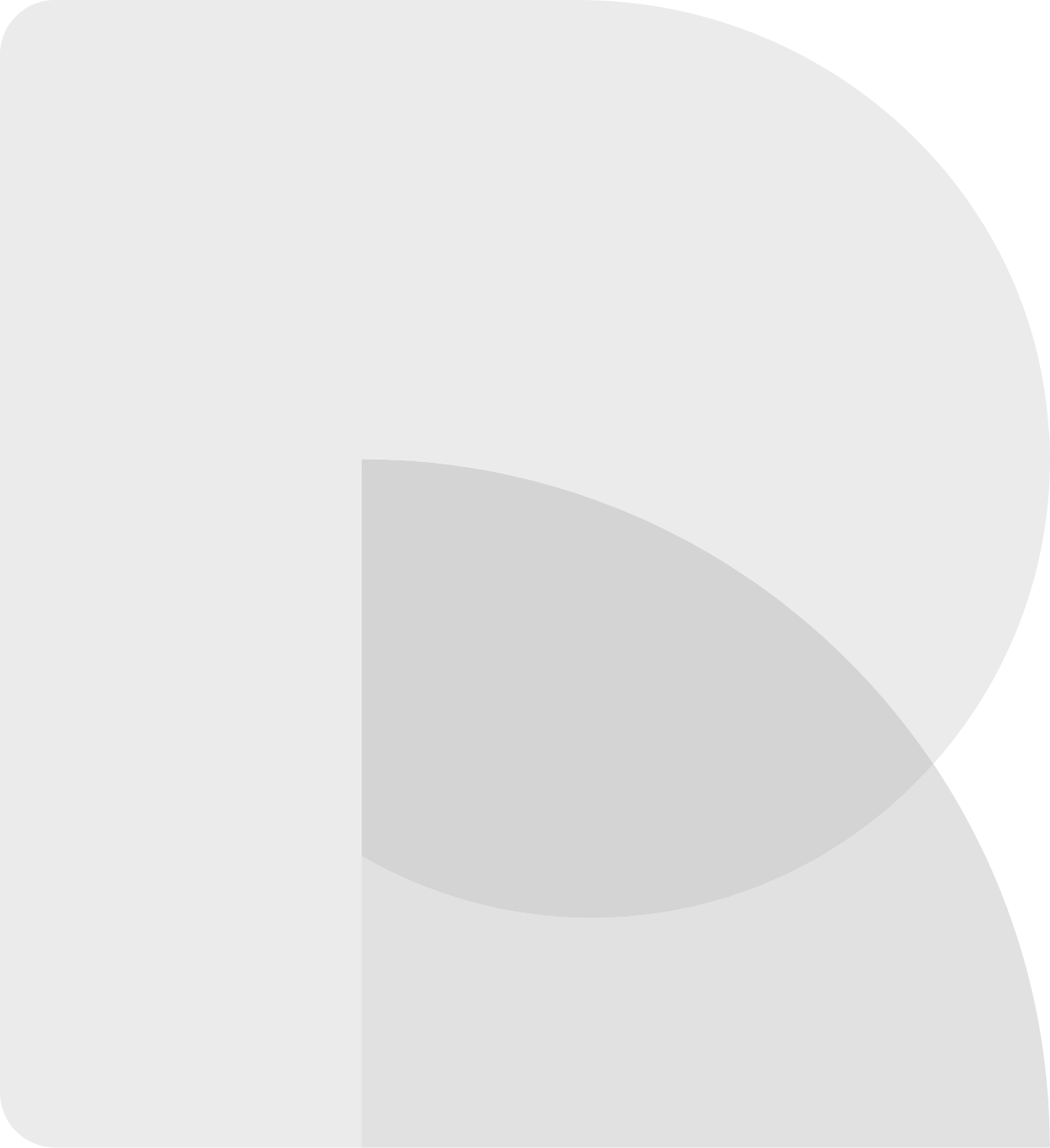
ウォルター・スウィートさん 戦略と粘り強さをもって資本を投じれば、法制定に匹敵する力を持つ ――フィランソロピー・アドバイザーの25年


プロフィール
Walter Sweet (ウォルター・スウィート)
Rockefeller Philanthropy Advisors 共同CEO兼プレジデント(Co-CEO & President)
約25年にわたり、Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) にてフィランソロピー・アドバイザーを務めたフィランソロピーの専門家。公衆衛生、コミュニティ開発、教育など、様々な課題分野を支援する財団やファミリーとの信頼関係を構築した豊富な経験を活かし、フィランソロピーを発展させるための規制や、ベストプラクティスを提供してきた実績を持ちます。ウォール・ストリート・ジャーナルやフィナンシャル・タイムズなど全国紙への寄稿、国内外のフィランソロピー・カンファレンスへの登壇、多数。コロンビア大学でアメリカ史の学士号を取得し、ニューヨーク・コミュニティ・トラストでプログラム・オフィサーを務めた経験を持ちます。
Rockefeller Philanthropy Advisors (RPA) は、2002年に設立された米国の非営利団体で、個人・家族・財団・企業に対して戦略的な寄付や助成活動を支援しています。始まりは、1891年にジョン・D・ロックフェラー・シニアが「ビジネスのようにフィランソロピーを管理する」という理念のもとに始めた慈善活動。現在では、年間5億ドル超の資金を扱い、70カ国以上で実績があり、フィランソロピーの戦略立案、プログラム運営、インパクト投資支援などを通じ、公正な社会の実現を目指しています。
日本では、フィランソロピー・アドバイザーズ株式会社のアドバイザーを務め、日本でのフィランソロピーの発展への貢献にも意欲を見せるウォルター。
今回は、彼がフィランソロピーの世界に入ったきっかけから、フィランソロピストやフィランソロピー・アドバイザーへの助言に至るまで、その豊富な経験に基づいた見解をご紹介します。
フィランソロピーの世界に入ったきっかけについて教えてください。
― 全くの偶然から、地域の人や企業がその地域課題を解決するコミュニティ財団に「これだ!」と直感。そこからフィランソロピーの道へ
正直なところ、ほんとうに偶然の出会いでした。学生の頃は歴史を専攻していて、特にアフリカ系アメリカ人の体験とか、社会にある不正義の構造に関心があったんです。当時は「社会を変えるなら、やっぱり政治」と思い込んでいて、民主党の選挙スタッフとして働き始めたんですが、いざ現場に入ってみると、想像以上に短期決戦で、腰を据えて深い課題に取り組むのは難しいと感じました。
そんなとき、友人の紹介でニューヨーク・コミュニティ・トラスト(NYCT)を訪れる機会があったんです。実は、それまで “コミュニティ財団” なんて、存在すら知らなかったのですが、特定の地域の課題解決を目的に、個人や企業からの寄付を集め、助成を通じて地域社会を支援する非営利組織に出会い、「あ、これだ!」とピンときたんです。課題を深掘りして、戦略的にお金を使って、成果を粘り強く追いかける――自分がやりたかった社会変革の “現場” はここだと。戦略と忍耐をもって資金を投じることは、新しい法律を成立させるのと同じくらい社会を動かせる――それから気づけばもう25年、この仕事を続けています。
日本でも若いフィランソロピストが登場し始めています。はじめはどのような経験が必要だと思いますか?
― 現場を知らないと机上の空論になるので、まずは現場を知る経験が必要
良いファンドマネジャーやVCが事業のリアルを分かってるように、資金提供する側にも「組織を動かしたことがあるか」はすごく大事だと思うんです。人を雇って、チームで成果を出す大変さを知っていれば、無理なKPIを押しつけたり、急に支援を打ち切ったりはしない。逆に、現場を知らずに理屈とデータだけで考えると、紙の上では完璧な戦略が、かえって現場を壊すことだってある。だから僕は、若い人にまずは現場にいくことをお勧めしています。
富裕層の次世代が、よりよいフィランソロピーを行うのに必要なことはなんでしょうか?
― まずは「お金と自分の価値観を結びつける練習」
やはり一番大切なのは、「お金と自分の価値観をどう結びつけるかを練習すること」だと思います。相続やIPOなどで突然大きな資産を持つことになった若い方が、「社会のために使いたいけれど、どう動けばいいか分からない」と戸惑うのは自然なことです。まずは自身のファミリーによる財団で小規模な助成を試してみるだけでも、資金の管理や成果の測り方、リスクをどこまで取るかといった感覚が、実体験として身についていきます。また、テクノロジーやインパクト投資に抵抗のない世代だからこそ、寄付・投資・事業を組み合わせた柔軟なアプローチを設計できるのも、大きな強みだと思います。
RPAが主に支援するのはどんなクライアントですか?
― 本気で難しい社会課題に取り組みたい人たち
端的に言えば、「本気で難しい課題を解きたい人」が僕たちのパートナーです。オペラに寄付するのも素晴らしいことですが、そこに私たちの出番はありません。ホームレス問題をどう減らすか、ネットゼロをどう加速するか、難病の治療アクセスをどう広げるか――そんな複雑で正解が一つではない課題に向き合うには、資金だけでなく、戦略やガバナンス、提携先まで含めて一体的に設計する必要があります。RPAでは、リサーチから理論構築、現場での検証、ファミリーガバナンスの設計まで、クライアントと一緒に取り組み、必要があれば資金の運用もお手伝いしています。
最近は「フィランソロピーを家族の結束のツールにしたい」というご相談も増えています。ビジネスで成功した創業者が、次世代と共通の体験を持つ場として社会貢献を選んでいます。私たちは、創業者が主導権を持ちつつ、子や孫も意思決定に関われる仕組みを設計します。それがうまくいくと、家族の対話が増え、社会へのインパクトも自然と広がっていきます。
印象に残っているプロジェクトを教えてください。
― 30億ドル財団の立ち上げや看護師不足解決の全国プロジェクトなど、大規模かつ複雑な案件
一つ目は、30億ドル規模のヘルス・コンバージョンの財団(非営利の病院や HMO、健康保険組織などが 営利企業に売却・転換 される際、その売却益や資産を原資に設立される 地域密着型の助成財団)の立ち上げでした。カトリック系の保険会社が売却された際、その利益を慈善信託に移すという案件で、信仰の価値観、州の規制、地域の医療ニーズの全てをバランスさせる必要がありました。社会的決定要因に注目して、貧困地区の子どもの栄養から高齢者の住環境まで包括的に投資し、行政と民間の協働モデルを形にできました。正直、胃が痛くなるような仕事でしたが(笑)、様々なステークホルダーとシステムを動かすことの面白さを実感しました。
二つ目は、全米に約1,000店舗を持つホームグッズチェーン創業一家との協働です。創業者から「寄付者に見過ごされがちな課題を選ぼう」という提案があり、リサーチの結果、看護師不足を解決テーマに据えました。奨学金、職場環境の改善、政策提言を組み合わせた統合プログラムを設計し、私たちはデータ分析、ステークホルダー調整、世代間ガバナンスまで伴走。家族全員が役割を持てる仕組みにしたことで、取り組みは全米へ拡大し、今でも規模と影響を伸ばし続けています。
優れたフィランソロピー・アドバイザーに欠かせない資質は何だと思いますか?
― 「制度の理解」「信頼関係の構築力」「エゴのコントロール」
まず欠かせないのは、助成規制や税制、最新のフィランソロピーのトレンドを押さえた「地図」を持っていることです。複雑な選択肢の中から最適な道筋を示すための知識と経験が求められます。
次に大事なのが、関係構築力。クライアントは日常的に “売り込み” を受けている立場なので、利害なく寄り添ってくれる第三者の存在はとても貴重です。
そして何より大切なのが、エゴのコントロール。寄付はあくまでクライアント自身の選択です。アドバイザーは、舵を取る「船長」ではなく、進むべき方向を照らす「灯台」のような存在であるべきだと思います。
この3つが揃ったとき、クライアントは安心して本音を語れ、結果として社会へのインパクトも大きく育っていきます。
この20年でフィランソロピー・アドバイザリー業界はどう変わりましたか?
― 寄付者にも見極める力が求められるように
僕がこの仕事を始めた頃、フィランソロピー・アドバイザーなんて本当に数えるほどしかいませんでした。でも今は、参入のハードルも下がって、スタイルもすごく多様になってきました。気候問題に特化してる人もいれば、国際人権だけに絞ってる人、ESG投資とセットでサービスを提供する人もいます。正直、ピンキリではありますが、選択肢が広がるのは健全なことだと思います。その分、寄付者自身にも「誰と組むか」を見極める目とリテラシーが求められるでしょう。
日本でフィランソロピーを始めたい人へのアドバイスはありますか?
― 現場を歩いて心が動く課題を見つけ、リスクとリターンを踏まえた支援をすることが大切
まずは、自分の足で現場を歩いて、心が動く課題を見つけてほしいと思います。リスクとリターンを理解したうえで資本を投入すれば、その取り組みには自然と持続力が生まれます。そして、寄付に限らず、仲間をつないだり、自分の影響力で政策対話を後押ししたり、専門知をボランティアで提供したりと、あなたのあらゆるリソースを活かしてください。あなたが持っている資源は、お金だけではないはずです。
お話を伺って...
2016年、インタビュアーの小柴が米国の大学院在学中に、正式なインターン枠がなかったにも関わらずRPAに私を迎え入れ、フィランソロピーの基礎と実践を惜しみなく教えてくれたのがウォルターです。
PA Inc.創業時も事業計画の壁打ちからネットワーク紹介まで手厚く支援いただき、今もアドバイザリーコミッティの一員として迷ったとき真っ先に相談する頼もしい存在。感謝は尽きません。
インタビュアー:Co-CEO 小柴優子
TOP