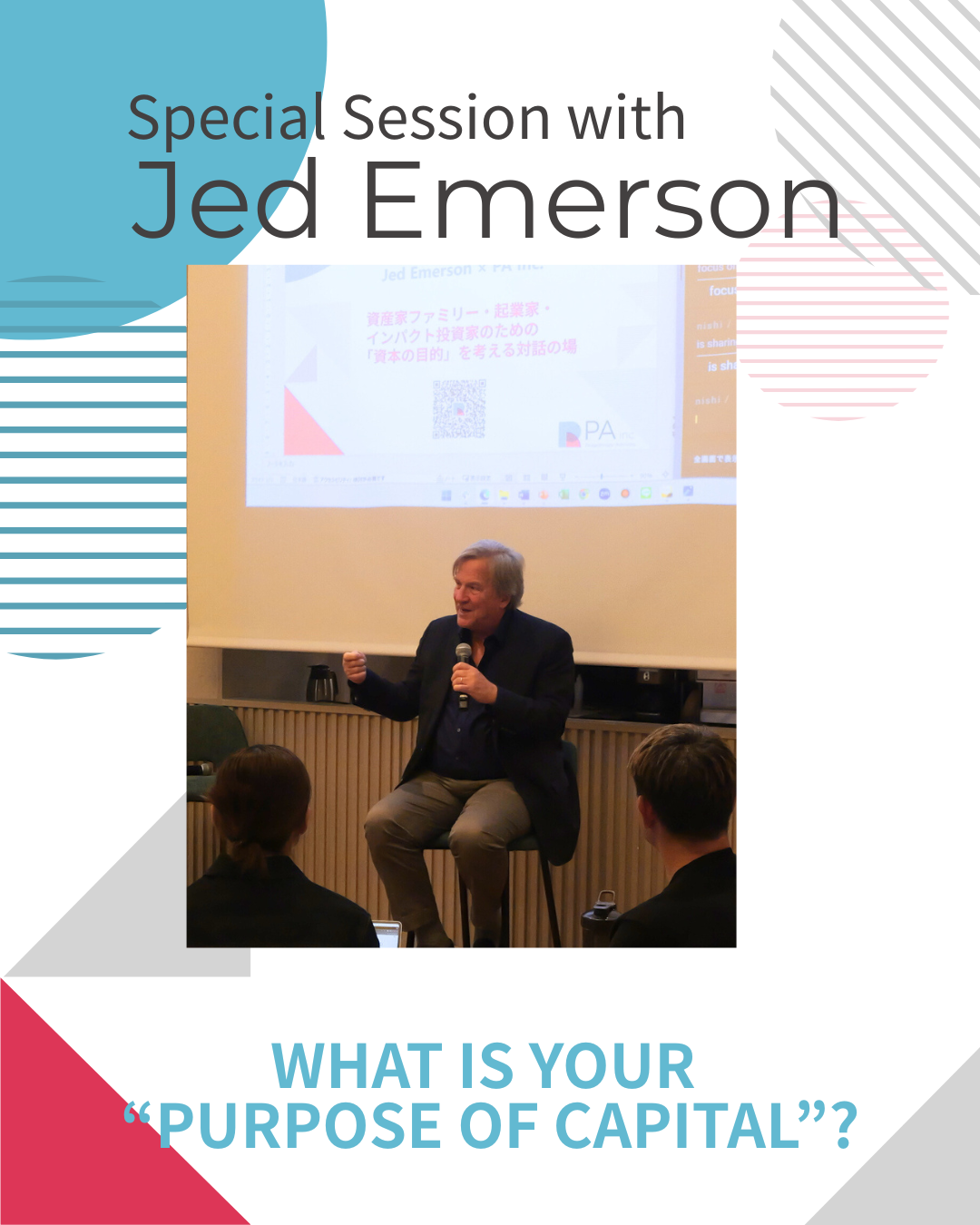KNOWLEDGE
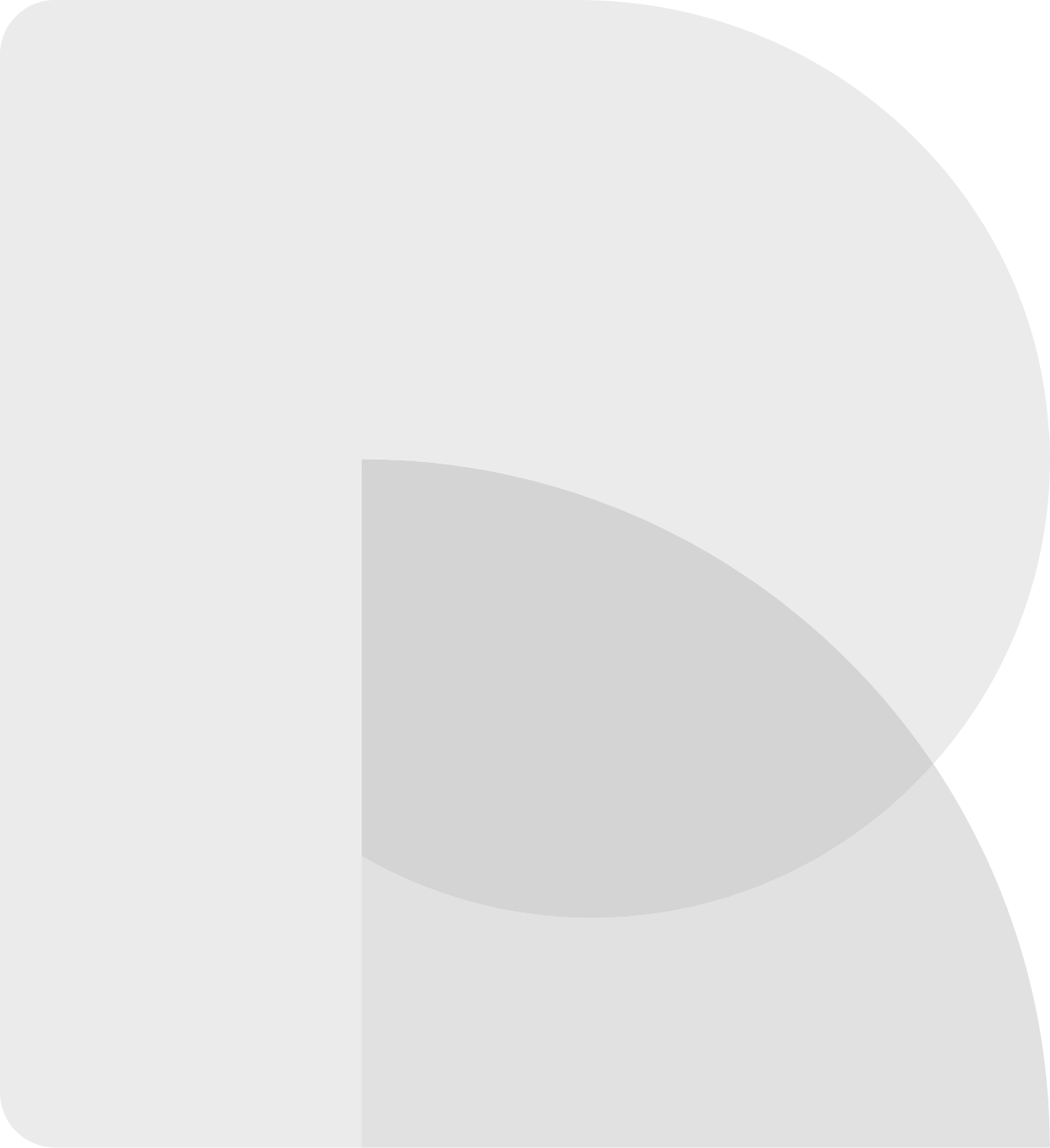
キョンスン・チャングさん 祖父の教えとともに、自らの道を歩む――投資やビジネスで挑む社会変革

プロフィール
Kyungsun Chung(キョンスン・チャング)
韓国ヒュンダイグループ創業家のファミリーメンバー。現在、現代海上火災保険のチーフ・サステナビリティ・オフィサーとして、戦略・リスク管理・デジタル変革・広報などを統括。ESG投資を手がけるプライベート・エクイティ「The Sylvan Group」の元マネージング・パートナーで、Rockefeller Philanthropy Advisorsの理事も務めた。韓国で社会的企業支援の非営利団体「Root Impact」を創設。コロンビア大学MBA。
若くして財閥ファミリーの立場と責任を背負いながら、フィランソロピーの道を歩み始めたキョンスンさん。
葛藤を抱えつつも、インパクト投資やビジネスの手法を通じて、自らの社会との関わり方を模索し、切り開いてこられました。今回は、そんな彼のフィランソロピーへの取り組みの変遷をお伺いします。
どのようにしてフィランソロピーの道に進まれたのですか?
― 大学時代に社会課題に関心を持ち、その後、ファミリー財団やNPOを通じて様々な角度から社会に関わるように
私の家族は韓国のHyundaiグループを築いた家系で、私は、いわゆる「財閥ファミリー」に育ちました。大学時代に社会問題やソーシャルビジネスの書籍を読む中で、社会起業家や非営利組織の役割に興味を持ち、「自分に与えられたリソースをどう活かし、社会へ還元できるか」を考え続けるようになりました。
その延長で2012年頃に設立されたファミリーの財団(Asan Nanum Foundation)に携わり、非営利やソーシャルセクターに関わる人々と多く出会うことで、自分が想像していた以上に大きな可能性を確信しました。その後、より幅広く「社会的インパクトを最大化するには何が必要か」を模索するために、自身でRoot ImpactというNPOを立ち上げたり、ソーシャルセクター向けのコワーキングスペース「Heyground」を設置したりと、様々な試みにチャレンジしています。
「財閥出身者としての使命感」はどのように形成されましたか?
― 「富は公器」。リソースを社会のために活かす責任を自覚
私の祖父(Hyundaiグループ創業者)からは「資産が一定の額を超えたら、それは自分個人のためというより社会的な“公器”として扱うべき」という考えを聞かされていました。若い頃は正直なところ「なぜそんなに社会還元が必要なのか」と具体的に分かっていなかった部分もありますが、大学の頃から社会問題に興味を持ち始め、それが必然的に「富はどう使われるべきか」という問いへつながりました。
すると祖父の考えが徐々に腑に落ちてきたんです。
さらに、非営利の現場では資金不足や人材不足といった制約もあり、「大きな資源を動かせるからこそ、できることがたくさんある」と実感しました。そして「インパクトを最大化する方法」は必ずしも寄付だけでなく、インパクト投資やビジネスの形態もありうる、というふうに視野を広げています。
なぜ独自の組織Root Impactを立ち上げたのですか?
― 柔軟に社会起業家を支援できる場としてのRoot Impact
当時、ファミリー財団は韓国国内でもかなり大きな規模でしたが、逆に規模が大きいがゆえに保守的にもなりやすかったんです。それは、私がまだ20代半ばの頃で、「もっと積極的にソーシャルビジネスを育てたい」「ソーシャルセクターのエコシステムを作りたい」と思っても、なかなか柔軟に動かせないことが多かった。そこで、財団とは別に、自分でNPOのRoot Impactを起ち上げ、より自由にアプローチできるようにしました。
特に「Heyground(ヘイグラウンド)」というコワーキングスペースでは、社会起業家やNPOが互いに刺激しあいながら働ける場所を提供しました。さらにコミュニティイベント、資金調達やスキルアップに関するサポートなど、必要なサービスを集中的に届けることで、ソーシャルセクター全体が成長できる「エコシステム」の実現を目指しました。
結果として、ソウル市内のソンス(聖水)地区がソーシャル関連のクラスターとして形成され、当時は官主導のイノベーションパークよりも成果が出た面もありました。そこから得た学びとしては、「多様なステークホルダーが自由に集い、自治しやすい環境を作ることが重要」ということです。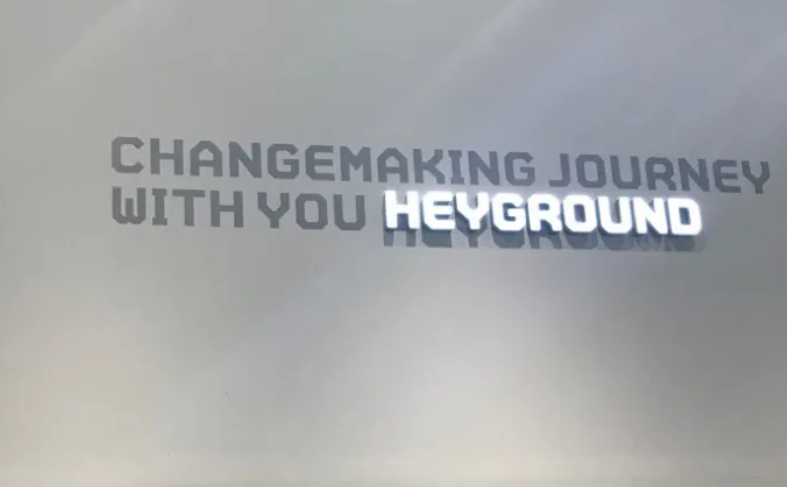
ヘイグラウンドのロビー壁に掲げられたスローガン 「Heygroundとともに、チェンジメイキングの旅を」
ヘイグラウンド外観
ヘイグラウンドの2フロアをつなぐ「ヘイ・ラウンジ」
ヘイグラウンドで開催された交流会:パタゴニア副社長リック・リッジウェイ氏を招いて
インパクト投資を始めた理由は何ですか?
― 非営利の限界を実感。より大きな社会的成果を、インパクト投資を通じて目指す
私自身がインパクト投資に踏み込んだ理由は、「寄付やNPOだけでは、支援規模やインパクトに限界がある」という実感からでした。投資の仕組みを活用すれば、より大きな事業展開を後押しでき、結果的に社会課題の解決を加速できるのでは、という期待があったのです。
たとえばヘルスケア関連では、シンガポールで整形外科や筋骨格系治療をワンストップ化する事業に投資しました。従来、患者さんが病院や施設を何か所も回らなければならない不便を解消し、治療費自体も抑えられる。こういう社会的意義の高いサービスを広げる投資ができたのは大きな成果でした。ただ、ファンドには制限があり、LP(出資者)の意向や一定期間でのエグジット(投資回収)要件など、長期視点の社会インパクトを考えると、必ずしも最適とはいえない面も感じました。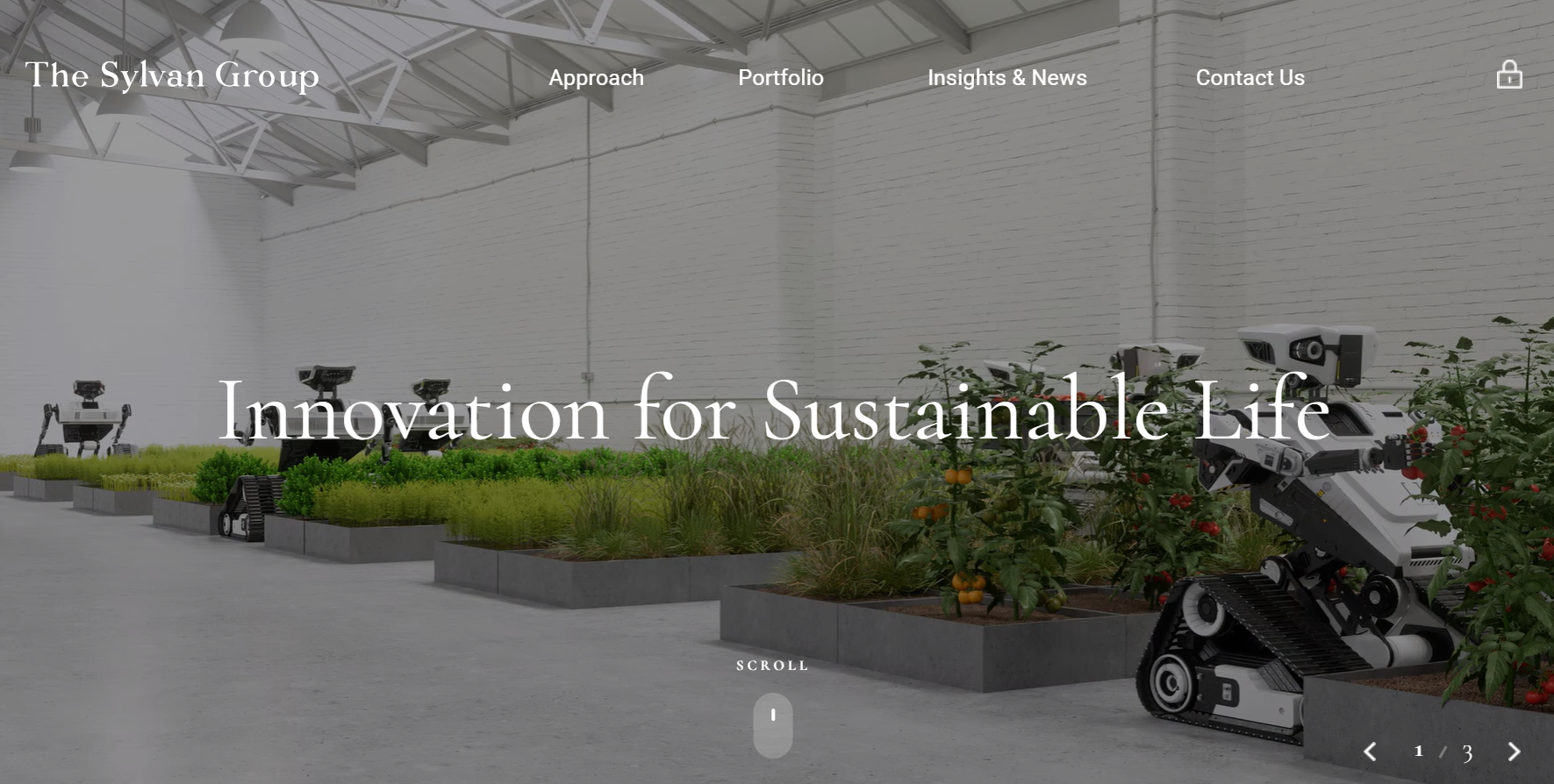
(出典:The Sylvan Group)
現在のビジネス領域での取り組みを教えてください。
― 企業の社会的責任と長期的インパクトの統合に挑戦
現在、ファミリービジネス本体のHyundai Marine & Fire Insurance(保険会社)では自動車保険、火災保険だけでなく健康保険まで幅広い商品を展開していますが、やはり社会的責任や長期的な視点が欠かせません。そのため、CSO(Chief Sustainability Officer)としてサステナビリティ推進全般に携わっています。具体的には、企業の社会貢献(CSR)活動や寄付プログラムの設計、ブランディングやコミュニケーション戦略など、いわば「企業が長期的に社会と共に持続していくために必要なこと」に取り組んでいます。
私自身はNPOでの経験が長いので、どうしても「短期的な収益を追うだけでは本当の意味での社会の持続性はない」という考えが強いのです。保険会社は長期的な視点が重要な業界なので、社会課題へのアプローチとも相性が良いはず。そういった意味では、企業の仕組みを最大限に活かして社会的インパクトを出していく方法を模索している段階と言えるでしょう。
地域活性化へのアプローチはどのような特徴がありますか?
― 地方都市での起業家支援や地域再生に、投資と寄付の両面から取り組む
現代自動車の本社があるウルサン(Ulsan)は、製造業の集積地で平均所得は高いものの、女性向けの雇用機会や新規事業が少なく、人口減少・高齢化が進む自治体でもあります。そこで企業のフィランソロピー予算(CSR)やインパクト投資を組み合わせ、「女性起業家が活躍できるインキュベーション環境づくり」をしようとしているところです。まだプロジェクト初期段階であり大きな成果はこれからですが、地域の方々と協力しながら進めています。
また、人口2万人ほどのヨンウォル(Yeongwol)という小さな自治体でも、ホテル事業への投資や若手アーティストの活動支援などを進め、地域再生モデルをつくろうとしています。ここは、かつて炭鉱で栄えた歴史ある町ですが、産業の衰退とともに人口が流出。そこに新しい魅力や雇用を生むことで地方創生の一助となればという考えです。
これからフィランソロピーに関わろうとする人々に、どのようなメッセージを伝えたいですか?
―「自分の原点」を見つめ、長期的な視野で社会課題に向き合うこと
まず、私が大事にしているのは「なぜこの社会課題に取り組みたいのか」という自分の “原点” をしっかりと認識することです。単に家や会社が大きいから、というだけでは続かない。自分自身の問題意識や責任感が大切だと思います。
そのうえで、ビジネスの知識や視点があるとフィランソロピーにおいても役立つ面は多いのですが、利益追求のロジックそのままでは、非営利セクターとの協働が難しいことも事実です。社会課題を解決するにはさまざまなステークホルダーと連携する必要がありますから、相手を尊重し、調整・説得し、ときに意見をぶつけあう姿勢も求められるでしょう。
結局は「自分の立場を、社会の持続性に活かしたい」という強い意思があるかどうかが重要になるのではないかと思います。ビジネス、投資、寄付、どの手法をとるにせよ、長期的視野で本質的に社会を良くしたいという気持ちがなければ意味がありません。「できる範囲でもっとやってみよう」という気持ちで、少しずつ行動を起こすことから始めるのがいいのではないでしょうか。
お話を伺って...
Kyungsun Chung氏の活動からは、「富は公器である」という哲学を出発点に、社会課題解決に挑む一貫した姿勢がにじみ出ていました。Root Impactの立ち上げに始まり、NPO、インパクト投資、さらには企業のCSR戦略に至るまで、多角的な手法を柔軟に使い分けながら、持続可能な社会づくりに取り組んでいます。
特に印象的だったのは、都市部だけでなく地方にも視点を向け、寄付と投資を組み合わせた再生モデルに挑戦している点。
事業と社会の間に垣根を設けず、どこまでインパクトを高められるかを常に模索するその姿勢は、これからのフィランソロピーの在り方に大きな示唆を与えてくれます。
インタビュアー:Co-CEO 小柴優子
TOP